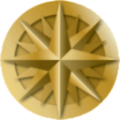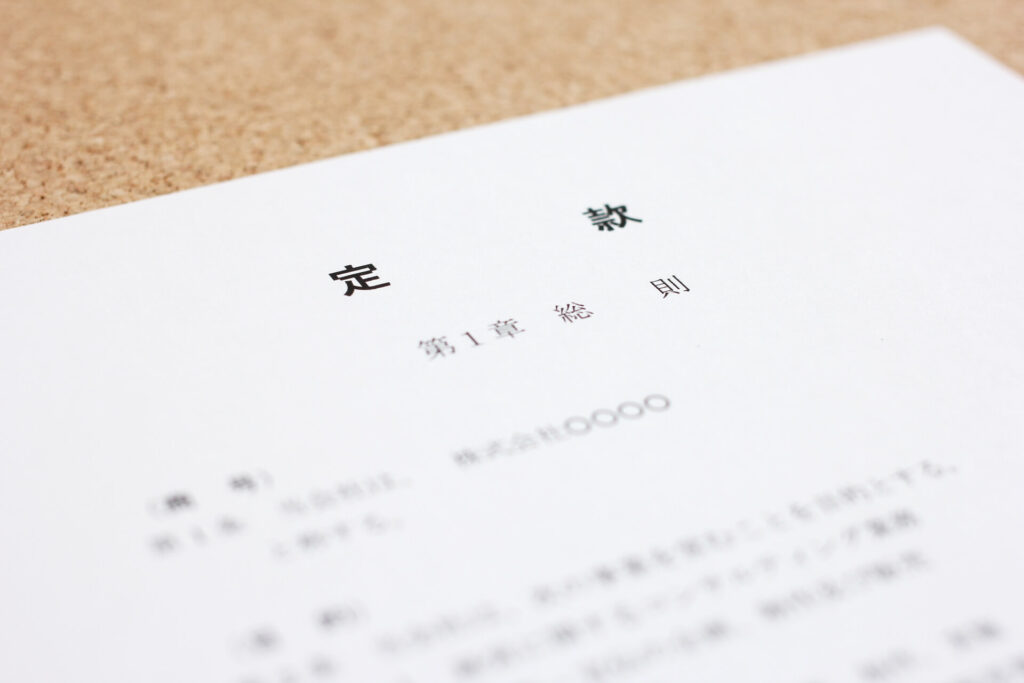
ご自身の会社の「定款」をご覧になったことがあるでしょうか。
定款には会社の法律上の根本規則が記載されています。
つまり、会社の「憲法」のようなものです。
普段の業務では使う場面がないため、会社設立時に作成して以来、一度も見たことがない方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、定款が必要となる場面は意外と多いものです。
具体的には、補助金・助成金の申請、行政への許認可申請、金融機関での口座開設、事業承継手続きなどです。
定款の規定を定める法律は幾度となく改正されており、定款に記載されている内容が現状にそぐわなくなっている可能性があります。
とくに株式に関する規程は早急に見直しておかないと、さまざまなトラブルを抱えかねません。
今回は、定款の株式に関する規定について解説します。
株式全部に譲渡制限が付けられているか
まずは株式の譲渡制限の有無を確認しましょう。
オーナー企業の場合、定款に「当社の株式の譲渡には取締役会の書面による承認が必要」と記載されていることがほとんどです。
しかし、社歴の長い企業の中には、譲渡制限を付けることができない時代の定款をそのまま放置している可能性があります。
譲渡制限を付けないと、
- 好ましくない株主が経営に口を出してくる
- 株式が分散する
- 「公開会社」扱いとなり、決算書作成に労力がかかる
といったデメリットが発生します。
※公開会社とは
全部または一部の株式について、譲渡制限がない株式を発行できると定款で定めている株式会社のこと。
株主は、株式会社の承認を必要とせずに自由に株式を譲渡・取得することができる。
すべての株式について、定款で譲渡制限している株式会社は非公開会社と呼ばれる。
株券不発行会社になっているか
現行の会社法では、株券は原則として「不発行」ですが、旧法下では「発行」が原則でした。
旧法下での定款には「当会社の発行する株式については、株券を発行するものとする。」という記載があるはずです。
これを「発行しないものとする」に変更する必要があります。
現物の株券があると、
- 株券の管理が煩雑になる(紛失リスク、管理コスト等)
- 第三者に株券が譲渡されてしまう
といったリスクが常に発生します。
2つ目については、とくに注意が必要です。
譲渡制限があっても取引自体は有効とみなされるからです。
つまり、株式会社の承認を得ずして株式を譲り受けた人は、会社に対して権利を主張することができないだけであって、株式を保有すること自体は何の問題もないのです。
そのような事態が起きる前に、第三者に株券を譲渡してしまいそうな株主から株式を買い取っておくなど、事前措置を講じておきましょう。
名義株が残っていないか
現行の会社法では、株式会社の発起人は1人でよいとされていますが、数十年前は、最低7人の発起人が必要な時代がありました。
発起人は最低1株を引受けなければならないため、社長が7人分の出資金を出して、名義だけを借りた名義株を発行しているケースがあります。
名義株は、一度でも配当金を支払っていると、実質的な株主の権利が確定します。
放置しておくと、名義株の所有者が株主としての権利を主張したり、株式の買取請求を求めてくる可能性があります。
事業承継対策を検討するような会社は、名義株発行当時より株価が数倍から数十倍になっていることが多いため、名義株の買い取りにまとまった資金が必要になります。
株式名簿で名義株の有無を確認し、早急に対処する必要があります。
最後に
冒頭で紹介したように、定款とは会社の「憲法」とも言うべき重要な書類です。
これまでに一度も定款を見直したことがない事業者は、現状にそぐわない内容になっている可能性が高いでしょう。
とくに「株式に関する規定」を古いままにしておくと、株式の相続が円滑に進まず、事業承継の足かせにならないとも限りません。
当会では「事業承継研究会」を立ち上げ、中小企業の円滑な事業承継を支援する活動を展開しています。
定款の見直しを含めた事業承継について相談を希望される方は、ぜひお問い合わせください。